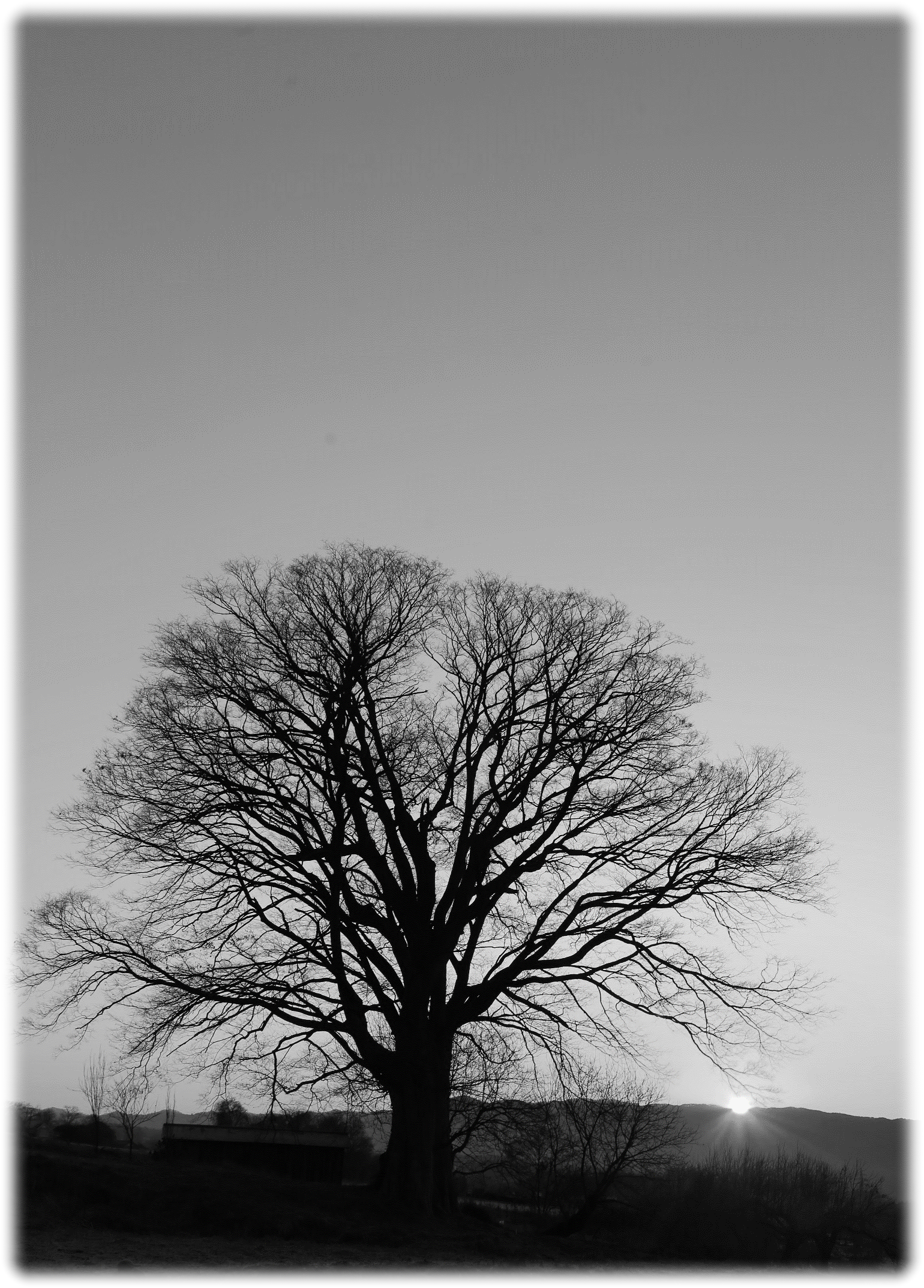5.聖書講話
「聖書における民族中心主義と多民族」
月本 昭男
プロフィール
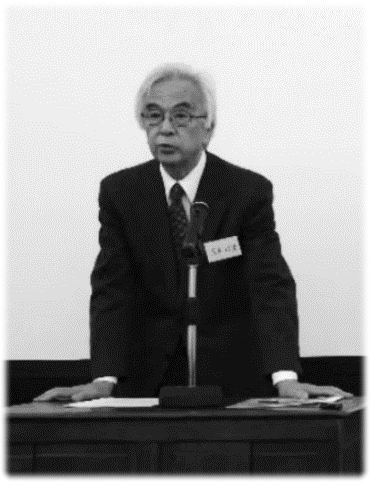 1948年、長野県生まれ。新島学園中学・高等学校(群馬県安中市)で学び、1971年、東京大学文学部卒、1980年、ドイツ・テュービンゲン大学修了。
1981~2014年、立教大学勤務、2014~2022年、上智大学神学部特任教授。専攻分野:旧約聖書学、古代オリエント学。この間、(公財)古代オリエント博物館館長などを兼任(2024年6月まで)、(公財)東京大学学生キリスト教青年会理事長、無教会研修所運営委員会代表。経堂聖書会所属。
最近の著書に『見えない神を信ずる』(日本キリスト教団出版局、2022年)、『物語としての旧約聖書』(NHK出版、2024年)など。
1948年、長野県生まれ。新島学園中学・高等学校(群馬県安中市)で学び、1971年、東京大学文学部卒、1980年、ドイツ・テュービンゲン大学修了。
1981~2014年、立教大学勤務、2014~2022年、上智大学神学部特任教授。専攻分野:旧約聖書学、古代オリエント学。この間、(公財)古代オリエント博物館館長などを兼任(2024年6月まで)、(公財)東京大学学生キリスト教青年会理事長、無教会研修所運営委員会代表。経堂聖書会所属。
最近の著書に『見えない神を信ずる』(日本キリスト教団出版局、2022年)、『物語としての旧約聖書』(NHK出版、2024年)など。
はじめに
経堂聖書会に連なっています月本昭男です。はじめに少しばかり自己紹介をさせていただくことをお許しください。幼い時、両親に連れられ、プリマス・ブレズレンと呼ばれる原理主義的福音派の集会で育ちました私は、高校時代、そこで教えられた信仰が正しいのかどうか、学問的に、客観的に確かめたいと思い、大学に進学しました。大学では、新約聖書から学びはじめましたが、前田護郎先生から、新約聖書学だけでは危ないよ、と聞かされ、新約聖書を正しく理解するには旧約聖書を学ぶ必要がある、と思いまして、まずは旧約聖書学に取り組みました。さらに、旧約聖書を理解するには古代オリエントを知らなければならない、と考え、古代オリエント学にまで足を踏み入れました。いずれ、新約聖書に戻りたい、と思いながら、半世紀余が経ってしまいました。
大学院時代は、日本聖書学研究所にて、主事をしておられた関根正雄先生から多くの刺激をいただきました。そして、ドイツ留学の機会が与えられましたとき、関根先生には「民族」の問題をしっかり考えて来ます、などとお手紙を差し上げたことを思い起こします。といいますのも、旧約聖書は、なによりも古代イスラエルの民の信仰が前面に出ているからですが、それと同時に、私自身の個人的な出自と関連して、民族という問題を抱えていたからでありました。
ところで、聖書における民族の問題を考えるとき、現代イスラエルのことを思わずにはいられません。昨年10月7日のハマスによる襲撃事件をきっかけにイスラエル軍のガザ侵攻がはじまり、いまだ終結の兆しは見えません。犠牲者の数は4万人を超えたと報じられています。キリスト者、非キリスト者を問わず、多くの方々が心を痛めています。パレスティナ問題の背後に宗教対立があるわけではありませんし、民族対立が先鋭化したというわけでもありません。じつは、イスラエル国籍を有するパレスティナ人は200万人余います。全人口の20パーセント余を占めています。多数派はイスラム教徒ですが。約7パーセントはいわゆるアラブ・クリスチャンです。西アジアの長い歴史のなかで、イスラム教徒とキリスト教徒とユダヤ教は、いさかいもなくはありませんでしたが、総じて申しますと、互いを認めつつ、平和裏に暮らしてきたのです。パレスティナ問題が発生したのは、20世紀に入ってからのことです。
現在イスラエルにおいてユダヤ系の人々は720万人といわれます。しかし、ユダヤ系といってもその出自はじつに様々です。最多はアシュケナジームと呼ばれる中部および東ヨーロッパ系ユダヤ人です。約300万人を数えます。スファラディームと呼ばれるスペイン系ユダヤ人の多くは、1492年のスペイン大迫害により、トルコをはじめ、アラブ圏に逃れましたが、1948年のイスラエル建国後、パレスティナに移住してきています。現在、モロッコ系が約40万人、イラク系が約45万人、イェーメン系が約44万人といわれています。そのほか、インド系、ジョージア系、クルド系、エチオピア系などのユダヤ人がそれぞれ10万人前後おり、さらにはソヴィエト連邦崩壊後、スラブ系ユダヤ人が150万人ほどイスラエルに移住しました。中国には、少数ながら、後8世紀頃から開封にユダヤ人コミュニティがあり、若い世代はイスラエルに移住しました。つまり、ユダヤ人と称する人々はヨーロッパ系からアフリカ系まで、白人から黒人まで存在しています。それは、彼らが世界各地で地域住民と婚姻関係を結んだことに起因します。
このような多様性が現代イスラエルのユダヤ人社会の特色であるといってよいのですが、じつは、ほぼ同様のことが旧約聖書のイスラエルの民にも言えるように思われます。そのことを指摘させていただくことが、本日の聖書講話の眼目となります。
(1)
前置きが長くなりましたが、旧約聖書を見てまいりましょう。旧約聖書には、しばしば、イスラエル民族中心主義が顔を覗かせます。たとえば、出エジプトを果たしたイスラエルの民は、しばらくシナイ山麓に逗留し、モーセを介して神ヤハウェと契約を結びますが、それに先立って、神ヤハウェはモーセに、この民に次のように告げよ、と命じています。すなわち、イスラエルの民は神ヤハウェの声に聞き従い、律法を守るならば、彼らはあらゆる民にまさる「わが宝の民」となり、「聖なる国民」となる、と(出19:5-6)。
約束の地に入る直前、モアブの野でモーセが民に告げた第2の律法といわれる申命記には、約束の地に入ったならば、イスラエルの民はそこに住む先住民と契約も婚姻関係も結んではならない、彼らを滅ぼし尽くさなければならない、と定められています(申7:1-3)。そして、出エジプト記と同じように、イスラエルは「聖なる民」であり、神ヤハウェは彼らを選んで「宝の民」とされた、と記されます(申7:6)。
こうした記述は古代イスラエルの選民思想と呼ばれてきました。もっとも、今日の日本でも、日本は「神の国」といった発言が政治家から飛び出すのですから、選民思想自体に驚くことはありません。ただし、旧約聖書にみる選民思想は、イスラエルの民が偉大な民族ではなく、ごく弱小の一民族、奴隷の民にすぎなかった、という点に、その特色があるといってよいでしょう。
それにしても、申命記には、カナンに住む民を滅ぼし尽くしなさい、という神の命令が伝わっており、実際、続くヨシュア記には、ヨシュアに率いられたイスラエルの民がカナンの先住諸民族を撃破して、カナンの地を獲得した記事が伝えられています。昨年10月から、かつてのカナンの地において、ヨシュア記の現代版でもあるかのような事態が進行していることは、まことに残念です。
そのヨシュア記の前半部には、ご存じのように、エリコとアイの攻略物語が伝えられています。エリコ攻略では、町の中にあるすべてを滅ぼし尽くし、男も女も、若者も老人も、牛、ヒツジ、ロバにいたるまで、すべて剣にかけた、と記されます(ヨシュ6:21)。アイについても、その住民を滅ぼし尽くしたといわれます(同8:24-26)。考古学に基づく研究成果からみますと、ヨシュアの時代、つまり後期青銅器時代から初期鉄器時代にかけて、じつは、エリコもアイもヨシュア記に物語られるような都市ではありませんでした。ですから、これらの物語の史実性は疑わしいのですが、仮にエリコとアイ攻略が史実に基づいていないとしても、住民を一人残らず殺害して終わる物語の主旨は変わりません。
物語において、念のために申しますと、神ヤハウェはヨシュアに「町をあなたの手に渡す」と告げますが、「ひとり残らず殺害せよ」と命ずることはありません。そうであっても、イスラエルによる全住民の殺害は、神の意思に沿った行動であったように物語られています。であれば、聖書に学ぶ私たちはこのような記事をどのように受けとめればよいのでしょうか。じつに悩ましい問題です。これについては、さしあたり、以下のように考えておきたいと思います。
1.旧約聖書の歴史伝承は、誰をも理想化せず、イスラエルさえも美化せず、
むしろ赤裸々な人間世界の現実を描き出す(旧約聖書の「リアリズム」)。
2.であればこそ、預言書や詩篇には武器を棄て、戦争を放棄する時代の到来が
将来に展望されることになる(イザ2:2-5、ゼカ9:9-10、詩46:9-11ほか)。
3.しかし、そのような理想世界は人間の努力によって実現するのではなく、
神の計画というか、神のはからいによる。ここに聖書の使信がある。
旧約聖書については、いえ新約聖書もふくめ、それが全体として語ろうとしていることを理解することが肝要です。それはヨシュア記自体にもいえることです。ヨシュア記が全体として何を伝えようとしたのか、考えてみましょう。
(2)
ヨシュア記から私たちは、イスラエルの民がカナン先住民を殲滅させ、カナン全地を獲得したかのような印象を受けます。ところが、丹念に読んでゆきますと、決してそうではないことがわかります。たとえば、エリコの遊女ラハブの一族はイスラエルの民の間に住み続けます(ヨシュ6:25「今日まで」)。欺いて、イスラエルの民と和平の契約を結ばせたギブオンの人々は、後に、イスラエルの民の間で一定の役割を果たすことになります(同9章)。それだけではありません。13章以下には、12部族への土地の分配が記されてゆきますが、ユダ部族領にはエブス人が住み続け(同15:63)、エフライム部族領では最大の都市といってよいゲゼルの住民を追い出さなかったといいます(同16:10)。マナセ部族もベト・シェアンをはじめタナクやメギドといった大きな都市の住民を追い出すことができていません(同17:11-13)。ヨセフの一族は低地の民が鉄の戦車を持っていたので、北イスラエルの穀倉地帯であるイズレエル平原を手に入れることができず、山間部に居住するしかなかったというのです(同17:14-18)。ダン部族については、彼らに配分された地域は彼らの領有にならなかったので、北に移動したと記されます(同19:40-48)。
このような事態をより明確に記すのは士師記第1章です。そこでは、部族ごとに、占領できなかった町の名が掲げられています。ユダ部族は、鉄の戦車をもつ低地の民を追い出せず、山間部に住むことになり(士1:19)、マナセは領土中の主要な都市を占領できず、北方の諸部族も同様でした。ダン部族は、逆に、アモリ人によって低地に降りることを許されなかったというのです。士師記1章は、カナン人がイスラエルの民の間に住み続けたというよりも、イスラエルの民がカナン先住民の間に住んでいたかのような印象を読者に与えます。
ヨシュア記は、カナン人がイスラエルが獲得した地に住み続けることもあったにせよ、全体として、イスラエルの民は部族ごとに土地の配分を受け、カナン全地がイスラエルの所有になった、と記されています。その土地は嗣業の地(協会共同訳は新改訳を踏襲し「相続地」)と呼ばれました。嗣業の地は神ヤハウェから授かった土地であり、究極的には神ヤハウェに属するがゆえに、自由な売買が禁ぜられる土地でした(レビ25:23以下)。ヨシュア記の物語はそのことを告げています。
士師記の主旨はそれとは異なります。士師記によれば、この時代、イスラエルの民はバアル神をはじめとするカナンの神々を慕ったがために、神ヤハウェによって周辺の民の手に渡される、という事態が繰り返されました。神ヤハウェがカナンの先住民を残したのは、じつは、イスラエルの民が神ヤハウェとの契約を守り通すかどうか、試すためであったというのです(士3:3-4)。しかし、イスラエルの民はその試みに耐えられませんでした。士師記はこのような時代を物語ります。そして、苦境に陥った民がヤハウェに叫び求めると、その都度、救済者(士師)が遣わされるのです。要するに、ヨシュア記と士師記は主題が異なっているということです。
(3)
士師記はもとより、ヨシュア記においても、イスラエルの民とカナン先住民との共存が示唆されていました。申命記7:1によれば、カナン先住民として7民族(ヘト、ギルガシ、アモリ、カナン、ペリジ、ヒビ、エブス)が名指しされています。後に触れるエズラ記には、国家を形成していたエジプト、モアブ、アンモンを別にすれば、カナン先住の5つの民族(カナン、ヘト、ペリジ、エブス、アモリ)があげられています(エズ9:1)。これらの民は王国時代の歴史記述に登場することはまずありませんが(例外はサム下24:7「テュルスのヒビ人とカナン人」、王上9:16「ゲゼルのカナン人」)、エズラ記9:1の記述が史実を反映しているとしますと、これらカナンの先住民たちは、王国時代を通じて、イスラエルの民と共存していたことになります。そこには、当然、イスラエルの民と彼らの間に婚姻関係も結ばれたに違いありません。そのことは、創世記において、父祖ヤコブの息子ユダがカナン人の娘をめとったこと(創37:1)、ルツ記において、エリメレクの家族が飢饉を逃れてモアブに移住し、2人の息子がモアブ人の娘を妻として迎えたこと(ルツ1:4)などに反映されています。
ところが、バビロニア捕囚から帰還したユダの民が神殿を建立し、神殿祭儀と律法とを中心とする宗教共同体が成立してゆきますと、異民族との結婚が神ヤハウェに対する背信行為とみなされました。そして、異民族と結婚していた者たちは強制的に離婚させられたのです。その経緯はエズラ記9章と10章に記されています。しかも、祭司の一族をはじめ、彼らと結婚していた者たちの名前まで列挙されています(エズ10:18以下)。ネヘミヤ記の末尾にも同様のことが書き留められています。理由は、ソロモンがそうであったように、異民族との結婚によって、異教の慣習がイスラエルに入り込む危険性があったからです。そうではあっても、異民族との結婚を宗教的な「罪」とみなして、これを忌避するという、狭隘で排他的なユダヤ民族の純血主義をここに見ないわけにはゆきません。
その一方で、そうした民族中心主義に異を唱えるかのような言葉も、旧約聖書には伝えられています。異邦の子らも宦官も、ヤハウェの律法(契約)を守るかぎり、ヤハウェに連なる民として受け入れられる、と告げる神ヤハウェの言葉がそれです(イザ56:3-8)。ここには、排他的なユダヤ民族中心主義に対する批判が込められているに相違ありません。そもそも、出エジプト伝承において、エジプトを出立した民は、壮年男子だけで60万人であったといいますが、それに続いて「雑多の人々が多数」混ざっていました(出エジプト12:38)。新共同訳は「種々雑多な人々」と訳し、「多くの」という形容詞を省略してしまいました。しかも、この「雑多の人々」と訳されるヘブライ語エーレブは、ネヘミヤ記13:3ではイスラエルの民から排除されねばならない「混血の者」(新共同訳、新改訳)、「混血の人」(協会共同訳)でした。出エジプト記によれば、エジプトの奴隷から解放されるイスラエルの民のなかに、そのような人たちが多数含まれていた、と記すのです。彼らは、エジプト脱出後、イスラエルの民と離別したのではありません。イスラエルに包摂されたのです。
自民族中心主義に必然的に伴う排他性を打破しようとする試みは、モーセ律法にもみることができます。新約聖書に語られる隣人愛の典拠となるレビ記19章がその代表的箇所でしょうか。「あなたは隣人をあなた自身のように愛しなさい」と命ずるレビ記19章18節は、新約聖書において最も重要な戒めとされますが、同じレビ記19章の終わりの部分34節で、あなたのもとに留まる寄留者はイスラエル人と同じであると定め、「あなたは彼(寄留者)をあなた自身のように愛しなさい」と命じています。「寄留者」と訳されるヘブライ語ゲールは、非イスラエル人でも、異なる部族出身者でもありうるのですけれど、ここでは「イスラエル人と同じである」と記されていますから、非イスラエル人を指していることは明らかです。
要するに、旧約聖書には、民族に関連して、一方に、狭隘で排他的な自民族中心主義があり、他方に、異邦の民を含み込む包摂主義がみられます。両者がそのまま併存しているといってよいのです。いずれの立場も、唯一神ヤハウェ信仰と結びついていました。前者は「選び」の信仰と結びつき、後者は神ヤハウェの普遍性に連なります。新約聖書が後者を受け継いだことはいうまでもありません。
(4)
イスラエルの民と異民族との関係において、出自が異民族と無関係でなかったのはダビデ王朝でした。ダビデはユダ部族出身であり、王朝の先祖はユダの息子ペレツに遡ります(ルツ4:18-22、代上2:4-15)。ペレツはヤコブの第3子ユダの息子ですが、ユダはカナン女性を妻とし、3人の息子をもうけます。そのユダが息子の妻として迎えたタマルと交わって、もうけた双子の1人がペレツでした。タマルの出自は記されていませんが、ふつうに読めば、カナン女性と判断されましょう(創38章)。
ダビデの曾祖母がモアブ女性ルツであったことも、よく知られています。モアブ人は、アブラハムの甥ロトとその娘との間に生まれた息子が名祖であった、と創世記は伝えています(創19:37)。イスラエル人の間では、モアブ人は近親相姦により産み落とされた汚らわしい民である、と理解されていました。そのモアブの女性がダビデの曾祖母でした。ダビデを継いだソロモンの母バトシェバの出自について、旧約聖書は沈黙していますが、王宮に召し抱えられる前はヘト人ウリヤの妻でしたから、非イスラエル人であった可能性が高いといえましょう。さらにソロモンを継ぐレハブアムの母はアンモン人であった、と列王記に明記されています(王上14:21)。このようにみますと、ダビデ王朝は、その最初期から、非イスラエル的要素が濃い王朝であったと申せましょう。
イスラエルの民は12部族から形成されていましたが、そのおおもとは、伝承によれば、別名イスラエルとも呼ばれたヤコブの12人の息子たちでした。そのなかで、妻が非イスラエル人であることを明示されるのは、ヨセフです。ヨセフはエジプトのオンの祭司の娘アセナトを妻に迎え、2人の息子マナセとエフライムを授かります(創41:45)。エフライムは後に北イスラエルを代表する有力部族となりますが、じつはエジプト人を母とする部族でした。そのほかには、エジプトに下るヤコブの一族を列挙するなかで、第2子シメオンの妻の1人はカナン女性でした(創46:10)。それ以外の息子たちの妻に関しては、旧約聖書は沈黙しています。なぜ、沈黙したのでしょうか。おそらく、明示することを意図的に控えたのです。
ヤコブは、末子ベニヤミン以外、すべての息子をパダン・アラムの親族ラバンのもとで授かっています。彼はラバンに7年間仕えた後、ラバンの娘レアを妻に迎えました。彼が愛したレアの妹ラケルを迎えるまでには、さらに7年待たねばなりませんでした。そして、レアの仕え女ジルパとラケルの仕え女ビルハをも妻とし、ラバンのもとで、都合、11人の息子をもうけます。そして、ラバンに仕えて20年後、一族を連れてカナンに戻りました(創31:18)。そうしますと、ヤコブの長子ルベンでさえも、カナンに戻ったときは13歳か12歳であったはずです。ですから、ごくふつうに考えますと、ヤコブの息子たちは、ヨセフを除いて、すべてカナンの地で妻を迎えたことになりましょう。そうであれば、ヤコブの息子の妻たちは、エジプト女性を妻に迎えたヨセフの場合を除き、すべて広義のカナン人であったことになります。それ以外の可能性は考えられません。しかし、このことを指摘している注解書を私はまだみていません。注解書は書かれていることは説明しますが、書かれていないことに注意を向けないからです。
要するに、イスラエルの民は、その出自からみて、後のユダヤ民族純血主義からは遠く隔たっていたことになります。旧約聖書は、しかし、ヤコブの息子たちの妻に関する事実をヴェールに包み込みました。しかし、問題意識をもってヤコブの物語を読めば、イスラエルの民が、当初から、そもそも雑種の民であったことは明らかではありませんか。私たちは、ときに、旧約聖書があえて沈黙していることを考えてみる必要があるのです。
イスラエルの民が雑種の民であったことは、旧約聖書のほかの箇所にも明示されています。申命記は、イスラエルの先祖が「アラム人」であったと伝えます(申26:25)。アラム人と言えば、王国時代、幾度も戦いを交えた民でした(列王記上20章ほか)。預言者エゼキエルは、エルサレムについて、あなたの生まれはカナン人、父はアモリ人、母はヘト人であった、と伝えています(エゼ16:45)。そもそも、出エジプトの民には「雑多の民が数多く」混じっていたことは、すでに触れたとおりです。
このようにみますと、旧約聖書には、偏狭で排他的な民族主義が枝を伸ばす一方で、随所に、他民族に開かれた姿勢が静かに根を張っていることがわかります。前者が唯一神による「選び」の信仰の片寄った形態であるとすれば、後者は同じ唯一神への信仰から異民族を自民族と同列にみる普遍的視座へと向かいます。
預言書にもその萌芽をみてとることができます。記述預言者の嚆矢(こうし)、アモスは「選民思想」に基づく同胞たちの楽観主義(アモ9:10「災いはわれらに近づくことも、襲うこともない」)に対して、イスラエルを相対化する言葉を残しました。アモス書9章7節にそれが窺われます。イスラエルの民は、神ヤハウェにとって、クシュの人々、ペリシテ人、アラム人と何ら変わるところがないではないか、というのです。地上の諸民族は神の前に平等に並んでいる、とアモスは受けとめました。
(5)
これまで、私はいささか細かいことにこだわりすぎたかもしれません。申し上げたかったことは、民族観念自体が歴史のなかで意図的につくられてゆくものであり、民族純血主義は一種の宗教化されたイデオロギーにすぎない、ということです。旧約聖書では、選民思想に裏打ちされたユダヤ純血主義がそうでした。しかし、そうした信仰を伝えたユダヤ人自身が流浪の民として世界に散るなかで(ディアスポラ「散在のユダヤ人」)、はじめに申しましたように、形質人類学的にはネグロイド(アフリカ系)、コーカサイド(アラブ系を含むインド・ヨーロッパ系)、モンゴロイド(アジア系)までを擁する多民族的な民となったのです。
しかし、本日の講話で私が申し上げたかったことは、それにつきません。ユダヤ中心主義を掲げた旧約聖書の民は、もう一方で、人類主義とでも呼びうる思想を残していました。そのことに触れないわけにはゆきません。
イザヤ書19章16節以下には、神ヤハウェに献げ物をする祭壇がエジプトに建てられ、そこからアッシリアにまで大路が敷かれ、イスラエルはエジプトとアッシリアに次ぐ第3の者となる、と記されます。イスラエルの民を苦しめたはずのエジプトとアッシリアがイスラエルに先立つような時代が展望されています。この背後には、イスラエルの神ヤハウェはあらゆる民族の神である、という全人類的視座がみてとれます。そうした全人類的視点は、じつは、旧約聖書の冒頭の原初史と呼ばれる箇所に見てとることができます。
それを私に気づかせてくれたのは丸山眞男でした。彼は「歴史意識の『古層』」という長大な論文によって、日本人の歴史意識を探求しましたが、そのはじめに『古事記』の「国生み神話」を取り上げ、創世記の天地創造物語と対比してみせたのです。天地創造物語には、「創造する」「ツクル」という動詞を重ねるのに対して、「国生み神話」には「ウム」「ナル」という動詞が繰り返されている。このことに着目し、「なりゆき」としての歴史といった日本特有の歴史観を明らかにしてみせました。私はそこから示唆を得て、あらためて天地創造物語と「国生み神話」を並べてみたのです。
すでにレジュメにも書きましたように、古事記と日本書紀が成立した奈良時代以前から、大和朝廷は中国大陸および朝鮮半島と数々の交渉をもち、仏教をとおしてインド(天竺)についても、シルクロードを介してペルシア(波斯)についても、情報を得ていました。それにもかかわらず、「国生み」神話には日本の国土のこと以外に記すことはありません。それとは対照的に、旧約聖書の天地創造物語には、またそれに続く「原初史」と呼ばれる物語群のなかには、これを伝えたイスラエルの民がいっさい登場しないのです。創世記10章は「民族表」と呼ばれ、当時のイスラエルに知られていた諸民族がノアの3人の息子の子孫として列挙されていますが、そこにもイスラエルという名はみられません。詳しく系図をたどれば、ノアの息子の1人セムの10代目にようやくアブラムが登場するのですが、イスラエルの民は数ある世界諸民族のなかの1民族にすぎません。全人類という視座から世界に目を向けているのです。このような視座が、世界を創造し、歴史を統べ治める唯一の神への信仰に発していることは、あらためて申し上げるまでもありません。
(6)
しかし創世記は、そのような原初史に続いて、イスラエルの父祖たちの物語を伝え、イスラエルの民が弱小の民でありながら、唯一の神に選ばれた民であることを伝えています。その父祖たちの物語を読みますと、彼らに神ヤハウェからの約束が与えられます。アブラハムには繰り返し(創12:2-3、13:14-15ほか)、イサクとヤコブには1回ずつ、約束が語られます(創26:4、28:13-14)。その約束は、土地の授与、子孫の増加、そして地上のあらゆる民の祝福の基となる、という3つの項目から成り立っています。
これらの約束については、旧約聖書が伝える古代イスラエルの歴史において成就したとみうるのかどうか、研究者の議論は分かれます。かつては、とくに土地の取得に関して、ヨシュア記において成就したのであり、歴史的にはダビデ・ソロモン時代を背景にする、といわれました(フォン・ラート)。しかし最近では、父祖たちのへの土地授与と子孫増加の約束はバビロニア捕囚期以降を背景にする、とみる研究者が多くなりました。いずれにしても、父祖たちの時代に土地授与と子孫増加の約束が実現しなかったことはたしかです。それゆえにヘブライ書の著者は、父祖たちは誰ひとり地上では約束のものは手に入れなかったが、じつは彼らは天の故郷に目を向けつつ、地上を歩んだのである、と記しました(ヘブ11:13、39)。
いずれにせよ、土地授与の約束を現在のパレスティナ問題に結びつけるのは言語道断です。ヨシュア記でさえ、イスラエルの民とカナン先住民の共存を示唆していることを忘れてはなりません。しかし、本日の聖書講話の最後に申し上げたいことは、父祖たちへの約束の3番目、すなわち「地上のあらゆる民があなたとあなたの子孫によって祝福を受ける」という神の約束です。私はこの約束には旧約聖書の神信仰の特色が現れている、と思うのです。
当時の西アジア世界を支配したアッシリア、バビロニア、ペルシアといった強大国は、自分たちが世界の支配者であることを誇りこそすれ、地上の諸民族の祝福の基となるとは考えませんでした。南の強大国エジプトも同様です。後のヨーロッパの文化を基礎づける思想と文学と芸術を残したギリシア人でさえ、自分たち以外の民をバルバロイ「野蛮な連中」と呼んで憚りませんでした。ところが、イスラエルの信仰者たちは、地上のあらゆる民族の祝福の基になる、との神の約束を伝えたのです。
イスラエルの民は古代オリエントの一弱小の民に過ぎませんでしたから、地上の全ての民の祝福の基となる、といった約束は弱小民族の一種の誇大妄想であるかのように響きます。しかし、それは世界を創造し、世界を差配する唯一の神を信ずる信仰に発していました。イスラエルの民はいかに弱小であろうとも、世界を差配する神に選ばれたからには、自分たちをとおして地上のあらゆる民族が祝福される、という人類史的な役割が与えられている、と自覚したのです。旧約聖書の唯一神信仰の重要な一側面がここにあります。
かつて内村鑑三は日本の「天職」に思いをはせ、1891年の「不敬」事件後、『余は如何にして基督信徒になりし乎』(1892年脱稿、刊行は1895年)によって個人の信仰問題を振り返るとともに、『地理学考』(1894年[明27]刊。後に『地人論』と改題)によって、東アジアに位置する日本の天職、すなわち日本が人類史上に果たすべく、神から与えられた役割について考察しました。曲がりなりにも内村の信仰を継承しようとする私たちは、こうした内村鑑三の視座をどのように受け継ぐのでしょうか。日本の天職などとは、私たちにとっては大げさに響くでしょうか。しかし、聖書の信仰に生かされている私たちは、パウロが記しましたように、信仰における「アブラハムの子孫」であり(ガラ3:29)、「神のイスラエル」(ガラ6:16)に連なります。であれば、キリスト者として私たちは、いかに弱く小さくあろうとも、私たちが生き生かされている世界に神の祝福を伝達する、また神の平和を造り出す器として用いていただこうではありませんか。そのことを申し上げて、拙い聖書講話の締めくくりとさせていただきます。
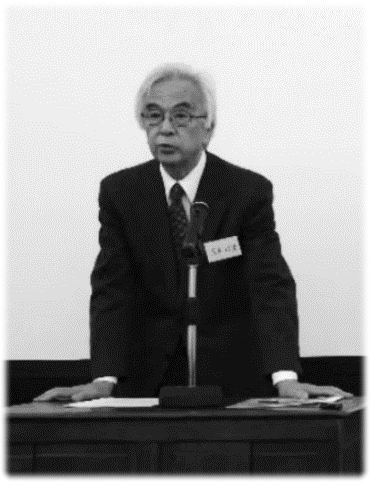 1948年、長野県生まれ。新島学園中学・高等学校(群馬県安中市)で学び、1971年、東京大学文学部卒、1980年、ドイツ・テュービンゲン大学修了。
1981~2014年、立教大学勤務、2014~2022年、上智大学神学部特任教授。専攻分野:旧約聖書学、古代オリエント学。この間、(公財)古代オリエント博物館館長などを兼任(2024年6月まで)、(公財)東京大学学生キリスト教青年会理事長、無教会研修所運営委員会代表。経堂聖書会所属。
最近の著書に『見えない神を信ずる』(日本キリスト教団出版局、2022年)、『物語としての旧約聖書』(NHK出版、2024年)など。
1948年、長野県生まれ。新島学園中学・高等学校(群馬県安中市)で学び、1971年、東京大学文学部卒、1980年、ドイツ・テュービンゲン大学修了。
1981~2014年、立教大学勤務、2014~2022年、上智大学神学部特任教授。専攻分野:旧約聖書学、古代オリエント学。この間、(公財)古代オリエント博物館館長などを兼任(2024年6月まで)、(公財)東京大学学生キリスト教青年会理事長、無教会研修所運営委員会代表。経堂聖書会所属。
最近の著書に『見えない神を信ずる』(日本キリスト教団出版局、2022年)、『物語としての旧約聖書』(NHK出版、2024年)など。
はじめに
経堂聖書会に連なっています月本昭男です。はじめに少しばかり自己紹介をさせていただくことをお許しください。幼い時、両親に連れられ、プリマス・ブレズレンと呼ばれる原理主義的福音派の集会で育ちました私は、高校時代、そこで教えられた信仰が正しいのかどうか、学問的に、客観的に確かめたいと思い、大学に進学しました。大学では、新約聖書から学びはじめましたが、前田護郎先生から、新約聖書学だけでは危ないよ、と聞かされ、新約聖書を正しく理解するには旧約聖書を学ぶ必要がある、と思いまして、まずは旧約聖書学に取り組みました。さらに、旧約聖書を理解するには古代オリエントを知らなければならない、と考え、古代オリエント学にまで足を踏み入れました。いずれ、新約聖書に戻りたい、と思いながら、半世紀余が経ってしまいました。
大学院時代は、日本聖書学研究所にて、主事をしておられた関根正雄先生から多くの刺激をいただきました。そして、ドイツ留学の機会が与えられましたとき、関根先生には「民族」の問題をしっかり考えて来ます、などとお手紙を差し上げたことを思い起こします。といいますのも、旧約聖書は、なによりも古代イスラエルの民の信仰が前面に出ているからですが、それと同時に、私自身の個人的な出自と関連して、民族という問題を抱えていたからでありました。
ところで、聖書における民族の問題を考えるとき、現代イスラエルのことを思わずにはいられません。昨年10月7日のハマスによる襲撃事件をきっかけにイスラエル軍のガザ侵攻がはじまり、いまだ終結の兆しは見えません。犠牲者の数は4万人を超えたと報じられています。キリスト者、非キリスト者を問わず、多くの方々が心を痛めています。パレスティナ問題の背後に宗教対立があるわけではありませんし、民族対立が先鋭化したというわけでもありません。じつは、イスラエル国籍を有するパレスティナ人は200万人余います。全人口の20パーセント余を占めています。多数派はイスラム教徒ですが。約7パーセントはいわゆるアラブ・クリスチャンです。西アジアの長い歴史のなかで、イスラム教徒とキリスト教徒とユダヤ教は、いさかいもなくはありませんでしたが、総じて申しますと、互いを認めつつ、平和裏に暮らしてきたのです。パレスティナ問題が発生したのは、20世紀に入ってからのことです。
現在イスラエルにおいてユダヤ系の人々は720万人といわれます。しかし、ユダヤ系といってもその出自はじつに様々です。最多はアシュケナジームと呼ばれる中部および東ヨーロッパ系ユダヤ人です。約300万人を数えます。スファラディームと呼ばれるスペイン系ユダヤ人の多くは、1492年のスペイン大迫害により、トルコをはじめ、アラブ圏に逃れましたが、1948年のイスラエル建国後、パレスティナに移住してきています。現在、モロッコ系が約40万人、イラク系が約45万人、イェーメン系が約44万人といわれています。そのほか、インド系、ジョージア系、クルド系、エチオピア系などのユダヤ人がそれぞれ10万人前後おり、さらにはソヴィエト連邦崩壊後、スラブ系ユダヤ人が150万人ほどイスラエルに移住しました。中国には、少数ながら、後8世紀頃から開封にユダヤ人コミュニティがあり、若い世代はイスラエルに移住しました。つまり、ユダヤ人と称する人々はヨーロッパ系からアフリカ系まで、白人から黒人まで存在しています。それは、彼らが世界各地で地域住民と婚姻関係を結んだことに起因します。
このような多様性が現代イスラエルのユダヤ人社会の特色であるといってよいのですが、じつは、ほぼ同様のことが旧約聖書のイスラエルの民にも言えるように思われます。そのことを指摘させていただくことが、本日の聖書講話の眼目となります。
(1)
前置きが長くなりましたが、旧約聖書を見てまいりましょう。旧約聖書には、しばしば、イスラエル民族中心主義が顔を覗かせます。たとえば、出エジプトを果たしたイスラエルの民は、しばらくシナイ山麓に逗留し、モーセを介して神ヤハウェと契約を結びますが、それに先立って、神ヤハウェはモーセに、この民に次のように告げよ、と命じています。すなわち、イスラエルの民は神ヤハウェの声に聞き従い、律法を守るならば、彼らはあらゆる民にまさる「わが宝の民」となり、「聖なる国民」となる、と(出19:5-6)。
約束の地に入る直前、モアブの野でモーセが民に告げた第2の律法といわれる申命記には、約束の地に入ったならば、イスラエルの民はそこに住む先住民と契約も婚姻関係も結んではならない、彼らを滅ぼし尽くさなければならない、と定められています(申7:1-3)。そして、出エジプト記と同じように、イスラエルは「聖なる民」であり、神ヤハウェは彼らを選んで「宝の民」とされた、と記されます(申7:6)。
こうした記述は古代イスラエルの選民思想と呼ばれてきました。もっとも、今日の日本でも、日本は「神の国」といった発言が政治家から飛び出すのですから、選民思想自体に驚くことはありません。ただし、旧約聖書にみる選民思想は、イスラエルの民が偉大な民族ではなく、ごく弱小の一民族、奴隷の民にすぎなかった、という点に、その特色があるといってよいでしょう。
それにしても、申命記には、カナンに住む民を滅ぼし尽くしなさい、という神の命令が伝わっており、実際、続くヨシュア記には、ヨシュアに率いられたイスラエルの民がカナンの先住諸民族を撃破して、カナンの地を獲得した記事が伝えられています。昨年10月から、かつてのカナンの地において、ヨシュア記の現代版でもあるかのような事態が進行していることは、まことに残念です。
そのヨシュア記の前半部には、ご存じのように、エリコとアイの攻略物語が伝えられています。エリコ攻略では、町の中にあるすべてを滅ぼし尽くし、男も女も、若者も老人も、牛、ヒツジ、ロバにいたるまで、すべて剣にかけた、と記されます(ヨシュ6:21)。アイについても、その住民を滅ぼし尽くしたといわれます(同8:24-26)。考古学に基づく研究成果からみますと、ヨシュアの時代、つまり後期青銅器時代から初期鉄器時代にかけて、じつは、エリコもアイもヨシュア記に物語られるような都市ではありませんでした。ですから、これらの物語の史実性は疑わしいのですが、仮にエリコとアイ攻略が史実に基づいていないとしても、住民を一人残らず殺害して終わる物語の主旨は変わりません。
物語において、念のために申しますと、神ヤハウェはヨシュアに「町をあなたの手に渡す」と告げますが、「ひとり残らず殺害せよ」と命ずることはありません。そうであっても、イスラエルによる全住民の殺害は、神の意思に沿った行動であったように物語られています。であれば、聖書に学ぶ私たちはこのような記事をどのように受けとめればよいのでしょうか。じつに悩ましい問題です。これについては、さしあたり、以下のように考えておきたいと思います。
1.旧約聖書の歴史伝承は、誰をも理想化せず、イスラエルさえも美化せず、
むしろ赤裸々な人間世界の現実を描き出す(旧約聖書の「リアリズム」)。
2.であればこそ、預言書や詩篇には武器を棄て、戦争を放棄する時代の到来が
将来に展望されることになる(イザ2:2-5、ゼカ9:9-10、詩46:9-11ほか)。
3.しかし、そのような理想世界は人間の努力によって実現するのではなく、
神の計画というか、神のはからいによる。ここに聖書の使信がある。
旧約聖書については、いえ新約聖書もふくめ、それが全体として語ろうとしていることを理解することが肝要です。それはヨシュア記自体にもいえることです。ヨシュア記が全体として何を伝えようとしたのか、考えてみましょう。
(2)
ヨシュア記から私たちは、イスラエルの民がカナン先住民を殲滅させ、カナン全地を獲得したかのような印象を受けます。ところが、丹念に読んでゆきますと、決してそうではないことがわかります。たとえば、エリコの遊女ラハブの一族はイスラエルの民の間に住み続けます(ヨシュ6:25「今日まで」)。欺いて、イスラエルの民と和平の契約を結ばせたギブオンの人々は、後に、イスラエルの民の間で一定の役割を果たすことになります(同9章)。それだけではありません。13章以下には、12部族への土地の分配が記されてゆきますが、ユダ部族領にはエブス人が住み続け(同15:63)、エフライム部族領では最大の都市といってよいゲゼルの住民を追い出さなかったといいます(同16:10)。マナセ部族もベト・シェアンをはじめタナクやメギドといった大きな都市の住民を追い出すことができていません(同17:11-13)。ヨセフの一族は低地の民が鉄の戦車を持っていたので、北イスラエルの穀倉地帯であるイズレエル平原を手に入れることができず、山間部に居住するしかなかったというのです(同17:14-18)。ダン部族については、彼らに配分された地域は彼らの領有にならなかったので、北に移動したと記されます(同19:40-48)。
このような事態をより明確に記すのは士師記第1章です。そこでは、部族ごとに、占領できなかった町の名が掲げられています。ユダ部族は、鉄の戦車をもつ低地の民を追い出せず、山間部に住むことになり(士1:19)、マナセは領土中の主要な都市を占領できず、北方の諸部族も同様でした。ダン部族は、逆に、アモリ人によって低地に降りることを許されなかったというのです。士師記1章は、カナン人がイスラエルの民の間に住み続けたというよりも、イスラエルの民がカナン先住民の間に住んでいたかのような印象を読者に与えます。
ヨシュア記は、カナン人がイスラエルが獲得した地に住み続けることもあったにせよ、全体として、イスラエルの民は部族ごとに土地の配分を受け、カナン全地がイスラエルの所有になった、と記されています。その土地は嗣業の地(協会共同訳は新改訳を踏襲し「相続地」)と呼ばれました。嗣業の地は神ヤハウェから授かった土地であり、究極的には神ヤハウェに属するがゆえに、自由な売買が禁ぜられる土地でした(レビ25:23以下)。ヨシュア記の物語はそのことを告げています。
士師記の主旨はそれとは異なります。士師記によれば、この時代、イスラエルの民はバアル神をはじめとするカナンの神々を慕ったがために、神ヤハウェによって周辺の民の手に渡される、という事態が繰り返されました。神ヤハウェがカナンの先住民を残したのは、じつは、イスラエルの民が神ヤハウェとの契約を守り通すかどうか、試すためであったというのです(士3:3-4)。しかし、イスラエルの民はその試みに耐えられませんでした。士師記はこのような時代を物語ります。そして、苦境に陥った民がヤハウェに叫び求めると、その都度、救済者(士師)が遣わされるのです。要するに、ヨシュア記と士師記は主題が異なっているということです。
(3)
士師記はもとより、ヨシュア記においても、イスラエルの民とカナン先住民との共存が示唆されていました。申命記7:1によれば、カナン先住民として7民族(ヘト、ギルガシ、アモリ、カナン、ペリジ、ヒビ、エブス)が名指しされています。後に触れるエズラ記には、国家を形成していたエジプト、モアブ、アンモンを別にすれば、カナン先住の5つの民族(カナン、ヘト、ペリジ、エブス、アモリ)があげられています(エズ9:1)。これらの民は王国時代の歴史記述に登場することはまずありませんが(例外はサム下24:7「テュルスのヒビ人とカナン人」、王上9:16「ゲゼルのカナン人」)、エズラ記9:1の記述が史実を反映しているとしますと、これらカナンの先住民たちは、王国時代を通じて、イスラエルの民と共存していたことになります。そこには、当然、イスラエルの民と彼らの間に婚姻関係も結ばれたに違いありません。そのことは、創世記において、父祖ヤコブの息子ユダがカナン人の娘をめとったこと(創37:1)、ルツ記において、エリメレクの家族が飢饉を逃れてモアブに移住し、2人の息子がモアブ人の娘を妻として迎えたこと(ルツ1:4)などに反映されています。
ところが、バビロニア捕囚から帰還したユダの民が神殿を建立し、神殿祭儀と律法とを中心とする宗教共同体が成立してゆきますと、異民族との結婚が神ヤハウェに対する背信行為とみなされました。そして、異民族と結婚していた者たちは強制的に離婚させられたのです。その経緯はエズラ記9章と10章に記されています。しかも、祭司の一族をはじめ、彼らと結婚していた者たちの名前まで列挙されています(エズ10:18以下)。ネヘミヤ記の末尾にも同様のことが書き留められています。理由は、ソロモンがそうであったように、異民族との結婚によって、異教の慣習がイスラエルに入り込む危険性があったからです。そうではあっても、異民族との結婚を宗教的な「罪」とみなして、これを忌避するという、狭隘で排他的なユダヤ民族の純血主義をここに見ないわけにはゆきません。
その一方で、そうした民族中心主義に異を唱えるかのような言葉も、旧約聖書には伝えられています。異邦の子らも宦官も、ヤハウェの律法(契約)を守るかぎり、ヤハウェに連なる民として受け入れられる、と告げる神ヤハウェの言葉がそれです(イザ56:3-8)。ここには、排他的なユダヤ民族中心主義に対する批判が込められているに相違ありません。そもそも、出エジプト伝承において、エジプトを出立した民は、壮年男子だけで60万人であったといいますが、それに続いて「雑多の人々が多数」混ざっていました(出エジプト12:38)。新共同訳は「種々雑多な人々」と訳し、「多くの」という形容詞を省略してしまいました。しかも、この「雑多の人々」と訳されるヘブライ語エーレブは、ネヘミヤ記13:3ではイスラエルの民から排除されねばならない「混血の者」(新共同訳、新改訳)、「混血の人」(協会共同訳)でした。出エジプト記によれば、エジプトの奴隷から解放されるイスラエルの民のなかに、そのような人たちが多数含まれていた、と記すのです。彼らは、エジプト脱出後、イスラエルの民と離別したのではありません。イスラエルに包摂されたのです。
自民族中心主義に必然的に伴う排他性を打破しようとする試みは、モーセ律法にもみることができます。新約聖書に語られる隣人愛の典拠となるレビ記19章がその代表的箇所でしょうか。「あなたは隣人をあなた自身のように愛しなさい」と命ずるレビ記19章18節は、新約聖書において最も重要な戒めとされますが、同じレビ記19章の終わりの部分34節で、あなたのもとに留まる寄留者はイスラエル人と同じであると定め、「あなたは彼(寄留者)をあなた自身のように愛しなさい」と命じています。「寄留者」と訳されるヘブライ語ゲールは、非イスラエル人でも、異なる部族出身者でもありうるのですけれど、ここでは「イスラエル人と同じである」と記されていますから、非イスラエル人を指していることは明らかです。
要するに、旧約聖書には、民族に関連して、一方に、狭隘で排他的な自民族中心主義があり、他方に、異邦の民を含み込む包摂主義がみられます。両者がそのまま併存しているといってよいのです。いずれの立場も、唯一神ヤハウェ信仰と結びついていました。前者は「選び」の信仰と結びつき、後者は神ヤハウェの普遍性に連なります。新約聖書が後者を受け継いだことはいうまでもありません。
(4)
イスラエルの民と異民族との関係において、出自が異民族と無関係でなかったのはダビデ王朝でした。ダビデはユダ部族出身であり、王朝の先祖はユダの息子ペレツに遡ります(ルツ4:18-22、代上2:4-15)。ペレツはヤコブの第3子ユダの息子ですが、ユダはカナン女性を妻とし、3人の息子をもうけます。そのユダが息子の妻として迎えたタマルと交わって、もうけた双子の1人がペレツでした。タマルの出自は記されていませんが、ふつうに読めば、カナン女性と判断されましょう(創38章)。
ダビデの曾祖母がモアブ女性ルツであったことも、よく知られています。モアブ人は、アブラハムの甥ロトとその娘との間に生まれた息子が名祖であった、と創世記は伝えています(創19:37)。イスラエル人の間では、モアブ人は近親相姦により産み落とされた汚らわしい民である、と理解されていました。そのモアブの女性がダビデの曾祖母でした。ダビデを継いだソロモンの母バトシェバの出自について、旧約聖書は沈黙していますが、王宮に召し抱えられる前はヘト人ウリヤの妻でしたから、非イスラエル人であった可能性が高いといえましょう。さらにソロモンを継ぐレハブアムの母はアンモン人であった、と列王記に明記されています(王上14:21)。このようにみますと、ダビデ王朝は、その最初期から、非イスラエル的要素が濃い王朝であったと申せましょう。
イスラエルの民は12部族から形成されていましたが、そのおおもとは、伝承によれば、別名イスラエルとも呼ばれたヤコブの12人の息子たちでした。そのなかで、妻が非イスラエル人であることを明示されるのは、ヨセフです。ヨセフはエジプトのオンの祭司の娘アセナトを妻に迎え、2人の息子マナセとエフライムを授かります(創41:45)。エフライムは後に北イスラエルを代表する有力部族となりますが、じつはエジプト人を母とする部族でした。そのほかには、エジプトに下るヤコブの一族を列挙するなかで、第2子シメオンの妻の1人はカナン女性でした(創46:10)。それ以外の息子たちの妻に関しては、旧約聖書は沈黙しています。なぜ、沈黙したのでしょうか。おそらく、明示することを意図的に控えたのです。
ヤコブは、末子ベニヤミン以外、すべての息子をパダン・アラムの親族ラバンのもとで授かっています。彼はラバンに7年間仕えた後、ラバンの娘レアを妻に迎えました。彼が愛したレアの妹ラケルを迎えるまでには、さらに7年待たねばなりませんでした。そして、レアの仕え女ジルパとラケルの仕え女ビルハをも妻とし、ラバンのもとで、都合、11人の息子をもうけます。そして、ラバンに仕えて20年後、一族を連れてカナンに戻りました(創31:18)。そうしますと、ヤコブの長子ルベンでさえも、カナンに戻ったときは13歳か12歳であったはずです。ですから、ごくふつうに考えますと、ヤコブの息子たちは、ヨセフを除いて、すべてカナンの地で妻を迎えたことになりましょう。そうであれば、ヤコブの息子の妻たちは、エジプト女性を妻に迎えたヨセフの場合を除き、すべて広義のカナン人であったことになります。それ以外の可能性は考えられません。しかし、このことを指摘している注解書を私はまだみていません。注解書は書かれていることは説明しますが、書かれていないことに注意を向けないからです。
要するに、イスラエルの民は、その出自からみて、後のユダヤ民族純血主義からは遠く隔たっていたことになります。旧約聖書は、しかし、ヤコブの息子たちの妻に関する事実をヴェールに包み込みました。しかし、問題意識をもってヤコブの物語を読めば、イスラエルの民が、当初から、そもそも雑種の民であったことは明らかではありませんか。私たちは、ときに、旧約聖書があえて沈黙していることを考えてみる必要があるのです。
イスラエルの民が雑種の民であったことは、旧約聖書のほかの箇所にも明示されています。申命記は、イスラエルの先祖が「アラム人」であったと伝えます(申26:25)。アラム人と言えば、王国時代、幾度も戦いを交えた民でした(列王記上20章ほか)。預言者エゼキエルは、エルサレムについて、あなたの生まれはカナン人、父はアモリ人、母はヘト人であった、と伝えています(エゼ16:45)。そもそも、出エジプトの民には「雑多の民が数多く」混じっていたことは、すでに触れたとおりです。
このようにみますと、旧約聖書には、偏狭で排他的な民族主義が枝を伸ばす一方で、随所に、他民族に開かれた姿勢が静かに根を張っていることがわかります。前者が唯一神による「選び」の信仰の片寄った形態であるとすれば、後者は同じ唯一神への信仰から異民族を自民族と同列にみる普遍的視座へと向かいます。
預言書にもその萌芽をみてとることができます。記述預言者の嚆矢(こうし)、アモスは「選民思想」に基づく同胞たちの楽観主義(アモ9:10「災いはわれらに近づくことも、襲うこともない」)に対して、イスラエルを相対化する言葉を残しました。アモス書9章7節にそれが窺われます。イスラエルの民は、神ヤハウェにとって、クシュの人々、ペリシテ人、アラム人と何ら変わるところがないではないか、というのです。地上の諸民族は神の前に平等に並んでいる、とアモスは受けとめました。
(5)
これまで、私はいささか細かいことにこだわりすぎたかもしれません。申し上げたかったことは、民族観念自体が歴史のなかで意図的につくられてゆくものであり、民族純血主義は一種の宗教化されたイデオロギーにすぎない、ということです。旧約聖書では、選民思想に裏打ちされたユダヤ純血主義がそうでした。しかし、そうした信仰を伝えたユダヤ人自身が流浪の民として世界に散るなかで(ディアスポラ「散在のユダヤ人」)、はじめに申しましたように、形質人類学的にはネグロイド(アフリカ系)、コーカサイド(アラブ系を含むインド・ヨーロッパ系)、モンゴロイド(アジア系)までを擁する多民族的な民となったのです。
しかし、本日の講話で私が申し上げたかったことは、それにつきません。ユダヤ中心主義を掲げた旧約聖書の民は、もう一方で、人類主義とでも呼びうる思想を残していました。そのことに触れないわけにはゆきません。
イザヤ書19章16節以下には、神ヤハウェに献げ物をする祭壇がエジプトに建てられ、そこからアッシリアにまで大路が敷かれ、イスラエルはエジプトとアッシリアに次ぐ第3の者となる、と記されます。イスラエルの民を苦しめたはずのエジプトとアッシリアがイスラエルに先立つような時代が展望されています。この背後には、イスラエルの神ヤハウェはあらゆる民族の神である、という全人類的視座がみてとれます。そうした全人類的視点は、じつは、旧約聖書の冒頭の原初史と呼ばれる箇所に見てとることができます。
それを私に気づかせてくれたのは丸山眞男でした。彼は「歴史意識の『古層』」という長大な論文によって、日本人の歴史意識を探求しましたが、そのはじめに『古事記』の「国生み神話」を取り上げ、創世記の天地創造物語と対比してみせたのです。天地創造物語には、「創造する」「ツクル」という動詞を重ねるのに対して、「国生み神話」には「ウム」「ナル」という動詞が繰り返されている。このことに着目し、「なりゆき」としての歴史といった日本特有の歴史観を明らかにしてみせました。私はそこから示唆を得て、あらためて天地創造物語と「国生み神話」を並べてみたのです。
すでにレジュメにも書きましたように、古事記と日本書紀が成立した奈良時代以前から、大和朝廷は中国大陸および朝鮮半島と数々の交渉をもち、仏教をとおしてインド(天竺)についても、シルクロードを介してペルシア(波斯)についても、情報を得ていました。それにもかかわらず、「国生み」神話には日本の国土のこと以外に記すことはありません。それとは対照的に、旧約聖書の天地創造物語には、またそれに続く「原初史」と呼ばれる物語群のなかには、これを伝えたイスラエルの民がいっさい登場しないのです。創世記10章は「民族表」と呼ばれ、当時のイスラエルに知られていた諸民族がノアの3人の息子の子孫として列挙されていますが、そこにもイスラエルという名はみられません。詳しく系図をたどれば、ノアの息子の1人セムの10代目にようやくアブラムが登場するのですが、イスラエルの民は数ある世界諸民族のなかの1民族にすぎません。全人類という視座から世界に目を向けているのです。このような視座が、世界を創造し、歴史を統べ治める唯一の神への信仰に発していることは、あらためて申し上げるまでもありません。
(6)
しかし創世記は、そのような原初史に続いて、イスラエルの父祖たちの物語を伝え、イスラエルの民が弱小の民でありながら、唯一の神に選ばれた民であることを伝えています。その父祖たちの物語を読みますと、彼らに神ヤハウェからの約束が与えられます。アブラハムには繰り返し(創12:2-3、13:14-15ほか)、イサクとヤコブには1回ずつ、約束が語られます(創26:4、28:13-14)。その約束は、土地の授与、子孫の増加、そして地上のあらゆる民の祝福の基となる、という3つの項目から成り立っています。
これらの約束については、旧約聖書が伝える古代イスラエルの歴史において成就したとみうるのかどうか、研究者の議論は分かれます。かつては、とくに土地の取得に関して、ヨシュア記において成就したのであり、歴史的にはダビデ・ソロモン時代を背景にする、といわれました(フォン・ラート)。しかし最近では、父祖たちのへの土地授与と子孫増加の約束はバビロニア捕囚期以降を背景にする、とみる研究者が多くなりました。いずれにしても、父祖たちの時代に土地授与と子孫増加の約束が実現しなかったことはたしかです。それゆえにヘブライ書の著者は、父祖たちは誰ひとり地上では約束のものは手に入れなかったが、じつは彼らは天の故郷に目を向けつつ、地上を歩んだのである、と記しました(ヘブ11:13、39)。
いずれにせよ、土地授与の約束を現在のパレスティナ問題に結びつけるのは言語道断です。ヨシュア記でさえ、イスラエルの民とカナン先住民の共存を示唆していることを忘れてはなりません。しかし、本日の聖書講話の最後に申し上げたいことは、父祖たちへの約束の3番目、すなわち「地上のあらゆる民があなたとあなたの子孫によって祝福を受ける」という神の約束です。私はこの約束には旧約聖書の神信仰の特色が現れている、と思うのです。
当時の西アジア世界を支配したアッシリア、バビロニア、ペルシアといった強大国は、自分たちが世界の支配者であることを誇りこそすれ、地上の諸民族の祝福の基となるとは考えませんでした。南の強大国エジプトも同様です。後のヨーロッパの文化を基礎づける思想と文学と芸術を残したギリシア人でさえ、自分たち以外の民をバルバロイ「野蛮な連中」と呼んで憚りませんでした。ところが、イスラエルの信仰者たちは、地上のあらゆる民族の祝福の基になる、との神の約束を伝えたのです。
イスラエルの民は古代オリエントの一弱小の民に過ぎませんでしたから、地上の全ての民の祝福の基となる、といった約束は弱小民族の一種の誇大妄想であるかのように響きます。しかし、それは世界を創造し、世界を差配する唯一の神を信ずる信仰に発していました。イスラエルの民はいかに弱小であろうとも、世界を差配する神に選ばれたからには、自分たちをとおして地上のあらゆる民族が祝福される、という人類史的な役割が与えられている、と自覚したのです。旧約聖書の唯一神信仰の重要な一側面がここにあります。
かつて内村鑑三は日本の「天職」に思いをはせ、1891年の「不敬」事件後、『余は如何にして基督信徒になりし乎』(1892年脱稿、刊行は1895年)によって個人の信仰問題を振り返るとともに、『地理学考』(1894年[明27]刊。後に『地人論』と改題)によって、東アジアに位置する日本の天職、すなわち日本が人類史上に果たすべく、神から与えられた役割について考察しました。曲がりなりにも内村の信仰を継承しようとする私たちは、こうした内村鑑三の視座をどのように受け継ぐのでしょうか。日本の天職などとは、私たちにとっては大げさに響くでしょうか。しかし、聖書の信仰に生かされている私たちは、パウロが記しましたように、信仰における「アブラハムの子孫」であり(ガラ3:29)、「神のイスラエル」(ガラ6:16)に連なります。であれば、キリスト者として私たちは、いかに弱く小さくあろうとも、私たちが生き生かされている世界に神の祝福を伝達する、また神の平和を造り出す器として用いていただこうではありませんか。そのことを申し上げて、拙い聖書講話の締めくくりとさせていただきます。